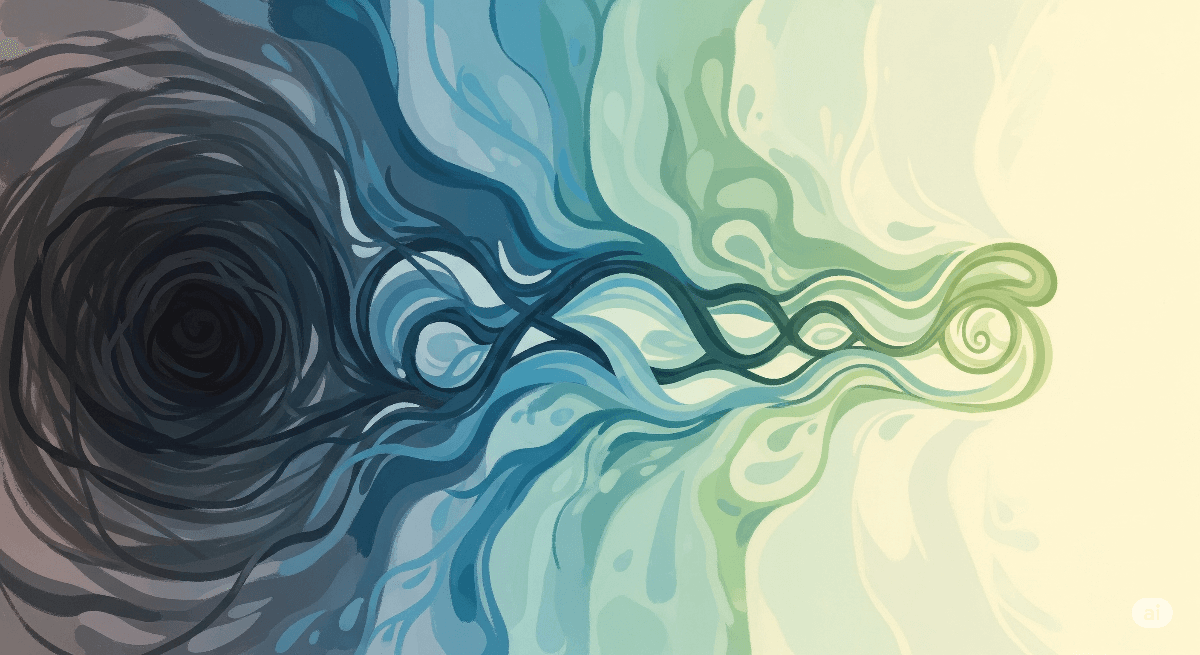子どもの成長は、親にとって大きな喜びであると同時に、言葉にできない不安をもたらすこともあります。特に、健診で「問題なし」と言われても、心の中に残る「何かおかしいな」という小さな違和感…。
今回は、長男が自閉スペクトラム症(ASD)と診断されるまでの、私たち家族の道のりをお話しします。
健診では問題なし…それでも消えない違和感
長男が生まれたときから、私はずっと心の中にほんの小さな違和感を抱えていました。他のことは少し違うように感じたのです。その小さな違和感を一部ご紹介します。
- 生後まもなく、まるでしっかりと見えているかのように目が合う
- いないいないばあなどの触れ合い遊びへの反応が薄い
- バイバイの仕方が、手のひらを自分の方へ向ける独特なもの(逆さバイバイ)だった
- 離乳食初期から偏食が目立った
- 手が汚れることを極端に嫌がり、手づかみ食べをほとんどしなかった
長男が1歳になり保育園に通い始めると、以前から感じていた違和感のほとんどは月齢が上がるにつれて目立たなくなり、家での子育てに大きな困りを感じることはありませんでした。保育園や健診でも特に指摘がなかったため、「きっとこの子は大丈夫」と自分に言い聞かせていました。
そんな矢先、2歳児クラスにあがった長男に転機が訪れます。保育園に定期的に巡回していた臨床心理士が、彼の行動に違和感を持ったというのです。担任の先生は「たまたま巡回の日にそういった行動があった」と言いながらも、その一度の巡回がきっかけとなり、長男はまだ診断がない段階で療育に通い始めることになりました。今思えば、担任の先生も日頃から何らかの違和感を感じていたのかもしれません。
療育で知った「子育てってこんなに楽になるんだ」
療育は週に1回の親子教室で、長男は半年ほど通いました。その効果はすぐに現れ、家での情緒が安定し、落ち着いて過ごせる日が増えていきました。
1人目の子育てだった私は長男の育てにくさに気づいていませんでした。しかし、療育を通じて、適切な関わり方を学ぶことで子育てが楽になることを知ったのです。「子育てって”こんなもん”じゃない」と、改めて気づかされました。
診断名を受け入れるまでの戸惑い
2歳児クラスの年度末、担任の先生から年少クラスに進級するにあたり、「加配(かはい)」をつけるかどうかの相談がありました。加配とは、集団生活で特別な配慮が必要な子どもに対し、保育士などの人員を追加する制度です。
先生は「加配がなくても大丈夫かもしれないし、もっと大きくなってから困りが出てくるかもしれない」と悩んでいました。いざ必要になった時にすぐにはつけられないとのことで、念のため手続きを始めることになりました。
この手続きのために初めて病院を受診し、長男は自閉スペクトラム症(ASD)と診断されました。医師からは「サポートを受けやすくするために、最近はすぐに診断を出すようにしている」と言われ、意外とあっさり診断が下りたことに驚きました。
先生の話では、いわゆる「発達グレーゾーン」に分類される長男でしたが、それでも診断名がついたことに対する戸惑いやショックは大きく、すぐに受け入れることはできませんでした。
診断名がついたことで、「この子をどう育てていけばいいのだろう」と悩んだり、未来への不安を感じることもありました。しかし、診断はゴールではなく、あくまでもスタート地点。適切なサポートを受けるための第一歩だと考えるようにしています。
もし、今同じように子育てに違和感を感じている方がいたら、一人で抱え込まず、専門家や同じ経験をした人に相談してみてください。あなたの違和感は、きっと子どもの成長を助ける大切なヒントになるはずです。